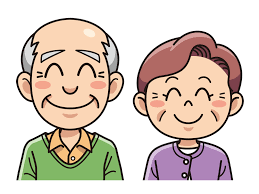急に冷え込んできたためか、今年は近くのハゼ並木も、自宅庭先のもみじも美しく色づいています。
あっという間の一年でした。
個人的なことですが、来年運転免許証の更新です。近くにある自動車学校で運転実技があり、教官に知人も多いので、失敗するわけにはいけません。ちょっとコンビニに行くのにも、歩いて行くには遠い郡部に住んでいるので、返納するには不便でまだ決心がつきません。それに加え、今年から、看護学校の講義に車で行っているので、当分運転はやめれません。事故に注意して運転を頑張るしかありません。
全自動運転が可能になるのは何年後でしょうね。
仕事の面では、認知症の新治療薬や、偏頭痛の注射剤など患者さんにとって有益な治療法が進んでいるようです。来年も、微力ながら続けて頑張りたいと思います。
みなさん、良いお年を
来年もよろしく。
院長 岡田和洋